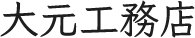自然と対峙しながらの暮らしに、強さを秘めて

自然と対峙しながらの暮らしに、強さを秘めて
少年の創造力に火を付けた
変色した壁の色が時間の流れを感じさせる、古びた家の模型。作り手は、現在40代半ばになる大元工務店の大元敏和社長です。
この模型は小学校6年生の夏休みの半分を費やした自由研究の作品で、今も羊蹄山の麓、倶知安町の実家に残されています。当時、たまたま手元にあった図面が載った家のパンフレットを見て、「へぇ〜、何だかおもしろそうだなぁ〜」と興味を持った敏和少年は、特別な知識がないにもかかわらず自力で図面を起こします。文房具店などで材料を揃え、模型作りに取り組み始めたら、すっかり夢中に。材料で足りないところは、例えば窓枠にはマッチ棒を使うなど、自分なりにいろいろな工夫もしました。
実家と交友のあった地元の建築会社の社長は、できあがった模型を見て、建築への興味と感覚を敏感に感じ取り「おお、好きなんだな。オレに預けれや」と早速、建築の世界に誘ってくれたといいます。この模型作りが、大元工務店の原点になったといっても過言ではないのかもしれません。

思い出がそこかしこに
大元社長が育った実家は、父・光弘さんが20歳前に自ら基本プランを作って建てた家。専門的な部分は大工さんをはじめとする職人さんたちに任せたとはいえ、そのストーリーはなかなかに壮大です。50年生の落葉樹をはじめとする家づくりで使う木は、山へ行って自ら切り倒し、馬そりに積んでは製材所へ。切り出した木は、少なくとも1年間寝かせて乾燥。屋根裏で使う木はあえて曲がったモノを選び、大人が立っても頭がぶつからないように配慮したといいます。
御歳75歳、サスペンダーがよく似合う粋な光弘さんが「川へ行って石を拾ってきたり、近所の人とコンクリートを練ったり、とにかく家は全部手づくり。どこもかしこも、思い出がいっぱいだね」と懐かしそうに話す隣で、大元社長は「家づくりの話になると、もう止まらなくなっちゃうから。子どもが3人なので、平屋では部屋が足りなくなって、増築して2階建てにしたけど、子どもたちは成長して独立したから空き部屋になっちゃったね」と、苦笑い。とはいえ、若いときからモノづくりに並々ならぬ情熱を傾けてきた父親の熱い血は、間違いなく息子に受け継がれているようです。

そこに手応えがあるから
家づくりも、農業も楽しい
模型作りで建築に目覚めた大元社長は、姉からの「一級建築士になればいい」というアドバイスを胸に秘めながら中学、高校時代を過ごし、大学に入っていよいよ建築の勉強を開始。卒業後、東京のゼネコンで工場やマンションの建設に関わったのち、道内の工務店に転職して一般住宅の建築を手がけます。そして今から13年前、それまで培った経験を踏まえて大元工務店を立ち上げました。リスクもある中、独立した理由を「人に使われるのが苦手でね。これもオヤジの影響かな」と笑います。
父の光弘さんは、ずっと農業の道で生きてきました。農家は、自営業。しかも思いどおりにならない自然を相手にする厳しい仕事です。しかしそんな自然と対話しながら何らかの解答を導きだすことが農業の手応えであり、楽しみでもあると光弘さんはいいます。それは、建築の仕事でも同じ。「お客様からは、想定外のこともいろいろ相談されます。でも、いいんです。必死に考えれば、何かしら解決方法が見つかります。自然を相手にしてきたオヤジを見てきたから、そう思えるのかもしれません」。どんな難問を振られても、お客様と一緒に最良の家づくりの方法を考えていくのが、大元工務店のスタンス。その原点は、光弘さんのとびきりの笑顔が物語る、前向きな生き方につながっていました。

手入れをして育むもの
だから「工務店はいらない」
「昔から床の下や屋根裏にもぐったり、壁を直したり、いつも家と向き合うオヤジの姿を見ながら育ってきました。だから、家はそういうものだって自然に思うようになりましたね」と大元社長はいいます。理想は、住み手が自分でつくり、自分で手入れをしながら永く愛着を持って暮らす家。それはまさに、父・光弘さんの家づくりそのものです。「極論ですが、工務店はいらないとさえ思うんです。自分でつくり、手を入れて、その家族にふさわしい家ができればいいのですから。ただお客様それぞれにライフスタイルがありますし、現実はそうはいきません。なので、私たちはそのお手伝いをさせていただいている、そんなふうに考えています」。
大元社長は、ささやかでも住み手が家に関わることが大事だといいます。壁を塗ったり、棚をつけたり、床のキズ消しをしたり…。自分たちで手をかけるごとに増す家への愛着、それこそが、ご家族にとって本当の意味での家の価値につながると信じているからです。
お客様が家づくりの主役。それを全力でサポートする大元工務店。これからも柔軟な発想でお客様と向き合いながら“ともに”理想の家をつくり続けます。